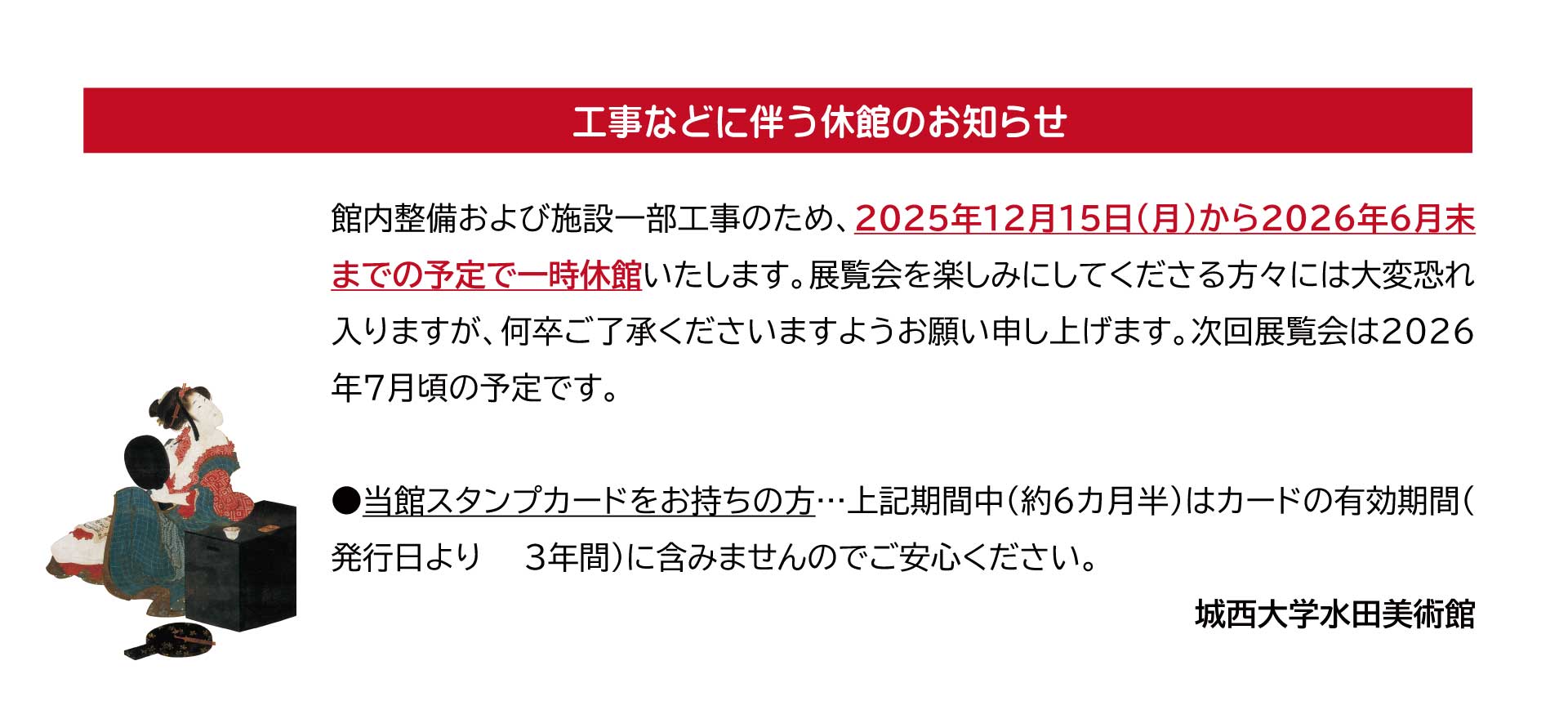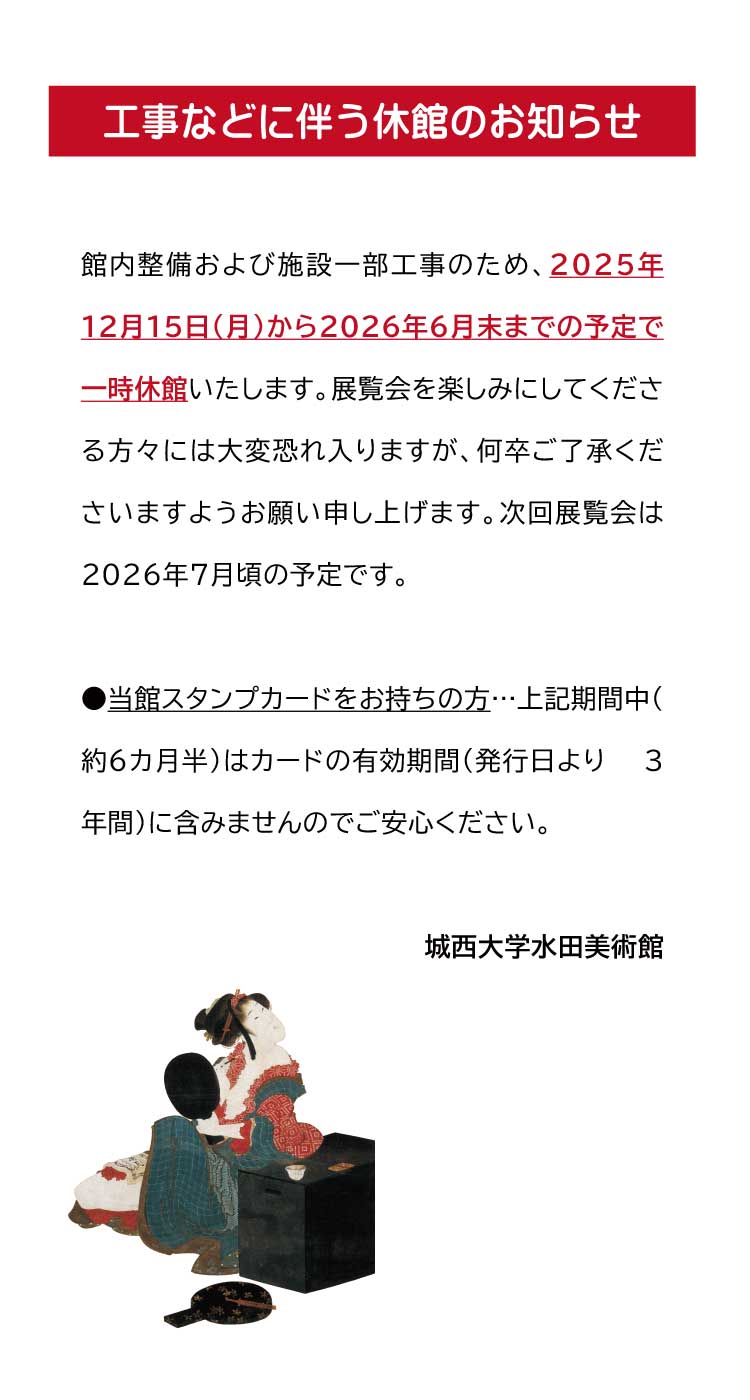お知らせ
-
2025年12月10日
-
2026年01月29日
-
2026年01月28日
-
2025年12月17日
展覧会情報
Exhibition
次回展覧会までお待ちください。
イベント情報
Event
開館情報
Schedule
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
休館日
- 開館日
- 休館日
- 展覧会
- イベント
ご利用案内
- 開館時間:9:30~16:30
入館は16時まで
休館日:開館日カレンダーを
ご覧ください。 - 城西大学水田美術館
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1