公開講座
城西大学および城西短期大学では教育研究の成果を広く地域に開放し、高度化、多様化する地域住民の学習意欲と地域社会のニーズに応えるために公開講座を開講しています。
2025年度
2025年度は「地域を元気にする城西大学の挑戦」のテーマで4講座を開講します。
第1回「健康食品のあれこれ~健康食品制度から大学での研究まで~」を開講しました
2025年9月3日(水)に第1回「健康食品のあれこれ~健康食品制度から大学での研究まで~」を開講しました。
開講式では、坂本武史副学長より「今回の公開講座で新しい知識や気づきを持ち帰っていただき、地域の未来を考えるきっかけになれば」と開講の挨拶がありました。
開講式では、坂本武史副学長より「今回の公開講座で新しい知識や気づきを持ち帰っていただき、地域の未来を考えるきっかけになれば」と開講の挨拶がありました。
講座の担当は、城西大学薬学部薬科学科の古旗賢二教授。日本における健康食品の実情から先生の研究分野まで、幅広い内容を紹介しました。
現在、日本の健康食品は保健機能食品として3つに区分されています。
①特定保健用食品(トクホ) ②機能性表示食品 ③栄養機能食品の3つです。
中でも国の厳しい審査が必要なトクホに代わり、届出だけで販売できる「機能性表示食品」は市場規模が年々拡大し、様々な商品が発売されています。ここで紹介されたのが「フードファディズム」という言葉です。これは食物や栄養が健康や病気に与える影響を過大に信じたり、評価することです。たくさんの健康食品の中から何が正しい情報なのかを自分で見極めることが大事だと説明しました。
健康な身体を作るには、バランスの取れた食事、適度な運動が大切。健康食品は正しい食生活を行うためのきっかけづくりと考えてほしいことを強調しました。
現在、日本の健康食品は保健機能食品として3つに区分されています。
①特定保健用食品(トクホ) ②機能性表示食品 ③栄養機能食品の3つです。
中でも国の厳しい審査が必要なトクホに代わり、届出だけで販売できる「機能性表示食品」は市場規模が年々拡大し、様々な商品が発売されています。ここで紹介されたのが「フードファディズム」という言葉です。これは食物や栄養が健康や病気に与える影響を過大に信じたり、評価することです。たくさんの健康食品の中から何が正しい情報なのかを自分で見極めることが大事だと説明しました。
健康な身体を作るには、バランスの取れた食事、適度な運動が大切。健康食品は正しい食生活を行うためのきっかけづくりと考えてほしいことを強調しました。
さらに先生の研究分野についてもお話があり、普段目にすることのない実験動画も紹介され、受講者の皆さんからは感心の声があがりました。
受講者の皆さんから「食べ物による健康を維持することに改めて考えさせられました。」「トクホと機能性表示食品の違いを再認識できました」などの声をいただきました。
受講者の皆さんから「食べ物による健康を維持することに改めて考えさせられました。」「トクホと機能性表示食品の違いを再認識できました」などの声をいただきました。
第2回「今日の気分はどうですか~感情に気づくと暮らしが変わる~」を開講しました
2025年9月10日(水)に第2回「今日の気分はどうですか~感情に気づくと暮らしが変わる~」を開講しました。
今回の講座の担当は、城西大学薬学部薬学科の吉田暁助教。
人間は進化の過程で喜びや悲しみ、怒りなどのさまざまな感情を身につけてきました。私たちはつい嫌なことが気になってしまったり、幸せが長続きしないと悩むことがありますがこの感情は人間が生き延びる上で必要なものと説明がありました。
今回の講座の担当は、城西大学薬学部薬学科の吉田暁助教。
人間は進化の過程で喜びや悲しみ、怒りなどのさまざまな感情を身につけてきました。私たちはつい嫌なことが気になってしまったり、幸せが長続きしないと悩むことがありますがこの感情は人間が生き延びる上で必要なものと説明がありました。

講義の後半では、表情を顔に出したり、実際に言葉にすることで不安や恐怖などが和らぐことが取り上げられました。受講者の方にご協力いただき、面白い実験もしました。笑いながら握力を測るのと怒った顔で握力を測るのはどちらが強くなるでしょう?正解は…怒った顔の方が強くなるでした!
これは笑うことで緊張がとれ、力が入りにくくなるからです。感情と身体が密接に関係していることが分かり、受講生の皆さんは納得の様子でした。
これは笑うことで緊張がとれ、力が入りにくくなるからです。感情と身体が密接に関係していることが分かり、受講生の皆さんは納得の様子でした。
感情とうまく付き合うには自分と一定の距離をとる、日記を書くこと、も有効との説明がありました。さらに共感性の高い人ほど、その人自身も幸せな感情を抱きやすいとも言いました。
「周りの人や自分自身に『今日の気分はどうですか?』と問いかけることで、明日はもっと良い日にしていきましょう」と語り、盛況のまま講座は終わりました。
受講者の皆さんからは「介護生活や健康などマイナスな気分になること、振り回されてしまうことがありますが、生活に取り入れ賢く生きられるようにしようと思いました。」「日記を毎日書いていますが、健康に良いとのことで引き続き実行したい」などの声が寄せられました。
「周りの人や自分自身に『今日の気分はどうですか?』と問いかけることで、明日はもっと良い日にしていきましょう」と語り、盛況のまま講座は終わりました。
受講者の皆さんからは「介護生活や健康などマイナスな気分になること、振り回されてしまうことがありますが、生活に取り入れ賢く生きられるようにしようと思いました。」「日記を毎日書いていますが、健康に良いとのことで引き続き実行したい」などの声が寄せられました。
第3回「地域産業活性化への城西大学の貢献~幹細胞培養上清液の利用~」を開講しました
2025年9月17日(水)に第3回「地域産業活性化への城西大学の貢献~幹細胞培養上清液の利用~」を開講しました。
今回の講座を担当するのは城西大学理学部化学・生命科学科の森田勇人教授。
森田先生の研究室では企業と共同研究をしており、その研究内容やそれを地域でどう活かしていくかを説明しました。
今回の講座を担当するのは城西大学理学部化学・生命科学科の森田勇人教授。
森田先生の研究室では企業と共同研究をしており、その研究内容やそれを地域でどう活かしていくかを説明しました。
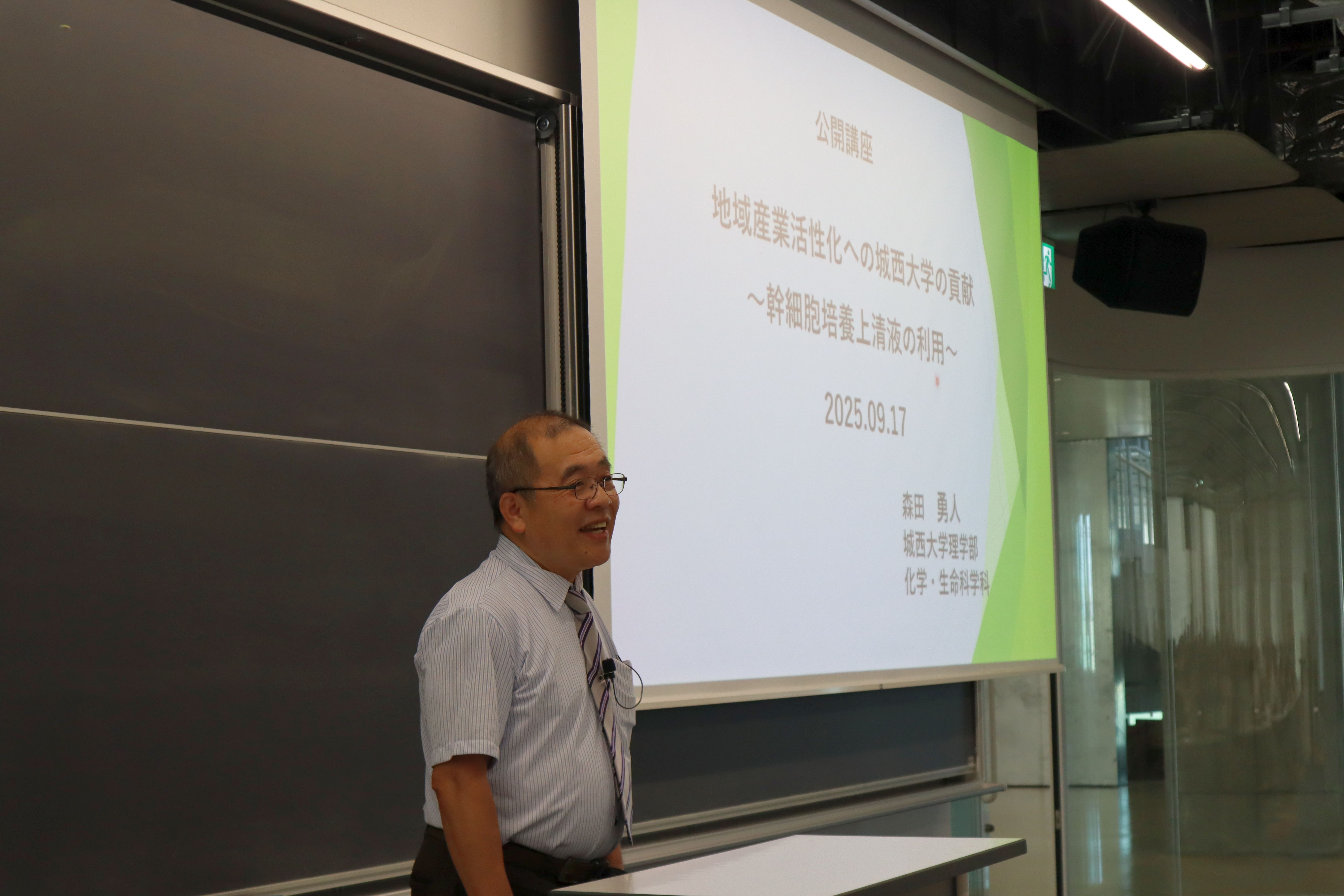
今回のテーマは「幹細胞培養上清液」。これは幹細胞を培養して幹細胞を取り除いて得られる上澄み液のことで、これには細胞を活性化させる成分が多く含まれています。講座ではその特徴や将来への活用法などが説明されました。
実際に細胞に上澄み液を加えることによって細胞が増殖していく実験動画を見た受講者からは驚きの声が上がっていました。
実際に細胞に上澄み液を加えることによって細胞が増殖していく実験動画を見た受講者からは驚きの声が上がっていました。

森田先生は「企業と共同研究することによる産学の地域連携から、その企業が所在する自治体を巻き込んだ産官学の地域連携への橋渡しができるように、大学の付加価値を高め存続していかなければならない」と語りました。
受講者の皆さんからは「大学が民間企業との共同研究により、地域の産業開発に貢献していくことはすばらしいです。」「研究が進み、雇用に繋がる企業の誘致が進み、地域の活性化を期待します。」などの声が寄せられました。
受講者の皆さんからは「大学が民間企業との共同研究により、地域の産業開発に貢献していくことはすばらしいです。」「研究が進み、雇用に繋がる企業の誘致が進み、地域の活性化を期待します。」などの声が寄せられました。
第4回「消滅可能性自治体を救え!~東秩父村における、『中山間ふるさと支援隊』としての経営学部三國ゼミナールの活動記録~」を開講しました
2025年9月24日(水)に第4回「消滅可能性自治体を救え!~東秩父村における、『中山間ふるさと支援隊』としての経営学部三國ゼミナールの活動記録~」を開講しました。
今回の講座の担当は、城西短期大学ビジネス総合学科・城西大学経営学部マネジメント総合学科 准教授の三國信夫先生。
三國先生のゼミでは「消滅可能性自治体」とされている埼玉県東秩父村の魅力を発見・発信し、地域を元気にする活動をしています。
今回の講座の担当は、城西短期大学ビジネス総合学科・城西大学経営学部マネジメント総合学科 准教授の三國信夫先生。
三國先生のゼミでは「消滅可能性自治体」とされている埼玉県東秩父村の魅力を発見・発信し、地域を元気にする活動をしています。
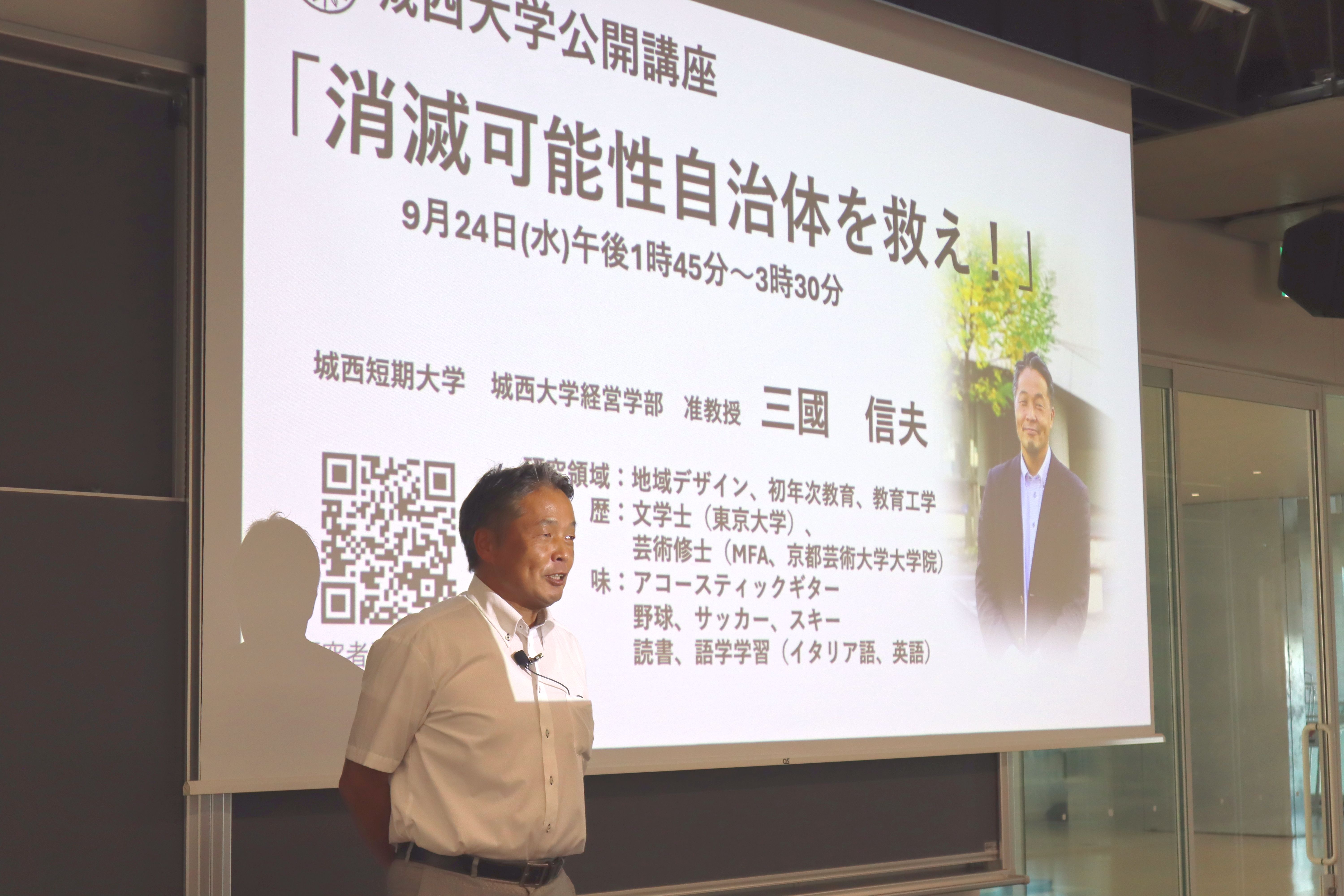


「消滅可能性自治体」とは2020年から2050年までの間に20-30代の女性人口が半分以下の水準まで減少すると予想されている自治体のことです。
三國先生のゼミは埼玉県から「ふるさと支援隊」として昨年度に続き選ばれて、東秩父村で村の方にインタビューをして、広報誌「東秩父村通信」を作成・配布したり、東秩父村の魅力を伝える動画やイベントを開催したりとさまざまな活動に取り組んでいます。今回三國先生と共に「ふるさと支援隊」としてのゼミ活動を報告してくれたゼミ生の小泉さんは「東秩父村でさまざまな方と話し、コミュニケーションを取る中で人とのつながりの大切さを学んだ」と活動に取り組んだ感想を話しました。
三國先生は「地域の方々との交流を大切にし、これからも学生と共に地域の課題に向き合っていきたい」と話しました。
受講者の皆さんからは「『ふるさと支援隊』として大学生が地域の課題に取り組んでいることを知り、感動した。今後もこの活動が広がっていくことを願っています。」「最近は東秩父村から足が遠のいていましたが、今回のお話を聴いてまた出かけてみようと思いました。」などの声が寄せられました。
受講者の皆さんにはご紹介できませんでしたが、講座終了時にさらに2名のゼミ生が駆けつけてくれました。三國ゼミ生の皆さん、ご協力ありがとうございました。
三國先生のゼミは埼玉県から「ふるさと支援隊」として昨年度に続き選ばれて、東秩父村で村の方にインタビューをして、広報誌「東秩父村通信」を作成・配布したり、東秩父村の魅力を伝える動画やイベントを開催したりとさまざまな活動に取り組んでいます。今回三國先生と共に「ふるさと支援隊」としてのゼミ活動を報告してくれたゼミ生の小泉さんは「東秩父村でさまざまな方と話し、コミュニケーションを取る中で人とのつながりの大切さを学んだ」と活動に取り組んだ感想を話しました。
三國先生は「地域の方々との交流を大切にし、これからも学生と共に地域の課題に向き合っていきたい」と話しました。
受講者の皆さんからは「『ふるさと支援隊』として大学生が地域の課題に取り組んでいることを知り、感動した。今後もこの活動が広がっていくことを願っています。」「最近は東秩父村から足が遠のいていましたが、今回のお話を聴いてまた出かけてみようと思いました。」などの声が寄せられました。
受講者の皆さんにはご紹介できませんでしたが、講座終了時にさらに2名のゼミ生が駆けつけてくれました。三國ゼミ生の皆さん、ご協力ありがとうございました。
閉講式では、倉成正和副学長より閉講の挨拶がありました。
今年度は222名の申込みがあり、104名が全4回を皆勤。その内の代表者に倉成副学長から修了証書が授与され、皆勤者には後日郵送することになりました。
来年度も開講を予定しています。今回ご参加いただいた方はもちろん、関心をお持ちの方もぜひご参加ください。
今年度は222名の申込みがあり、104名が全4回を皆勤。その内の代表者に倉成副学長から修了証書が授与され、皆勤者には後日郵送することになりました。
来年度も開講を予定しています。今回ご参加いただいた方はもちろん、関心をお持ちの方もぜひご参加ください。
城西大学・城西短期大学 地域連携センター事務室













